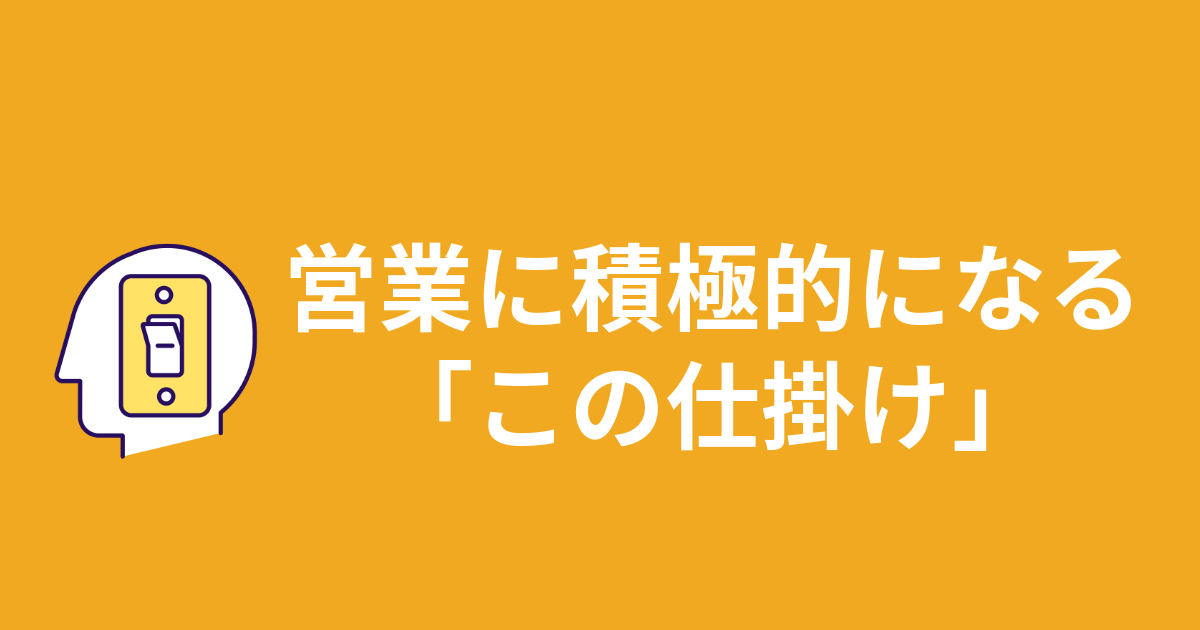リハビリ職の営業で起きる問題1
リハビリ事業のなかでも、通所リハビリや訪問リハビリ、通所介護に関しては、「開設すれば自動的に利用者が集まってくる…」なんてことはなく、利用者は自力で集客しなければなりません。
介護事業はほとんどがケアマネジャーからの「紹介」なので、「紹介型のビジネスモデル」です。つまり、自分たちで直接利用者を獲得するのではなく、まずはケアマネジャーに紹介される必要があります。
よって、集客はまず、
「ケアマネジャーに利用者の紹介をお願いする」
ところから始めます。
次に
「これを誰がするか」
ということですが、通所リハビリや訪問リハビリの場合は、リハビリ職が行うことが多いです。
ここで「大きな課題」が発生します。
それは、リハビリ職には営業の経験なんてないということです。
リハビリ職の営業で起きる問題2
ましてや、病院勤務の経験があるリハビリ職は「リハビリの先生」だったわけです。しかも、病院では、医師の処方が出てからリハビリを始めるため、基本的には受け身です。
よって、自分から患者を探したり、増やしたりすることはなく、リハビリの先生として、医師の処方が出るまで、患者を「待っている」のです。
そんな受け身のリハビリ職を、ただ通所や訪問に配置すると一体どうなるのでしょうか?
そうです。「待つ」のです。
でも、何もせずに待っているとサボっているように思われますから、手作りでものすごく時間をかけて、一応、パンフレットを作ります。また、今後使うか使わないかも分からない書類を作ったりもします。
しかし、地域のケアマネジャーは、新しくできた通所リハビリや訪問リハビリの存在を知らないわけですから、紹介は来ません。
そこで、経営者がしびれを切らして「営業に行きなさい」と指示を出しますが、それでも1日に1~2件程度しか営業に行かず、また部屋にこもってパンフレットや書類を作ります。
集客に伸び悩む通所リハビリや訪問リハビリの多くは、このパターンがめちゃくちゃ多いです。
営業に行かない、行けない悪循環を断ち切る方法
ですが、「これを解決する方法」があります。それは、リハビリ職の「集客に対する意識を変えること」です。
なぜ、リハビリ職が営業に行きたがないかというと、理由は次の2点です。
- .何を話せばよいのか分からない
- 自分の営業トークで、紹介してもらえる自信がない
この2点です。
リハビリ職は営業経験がないため、ケアマネジャーに対して「言葉巧みにトークして紹介してもらおう」と思ってしまいます。でも、そんなことできるわけありません。
そこで、ぼくは、これを解決するために、ある「仕掛け」をします。
すると、
・リハビリ職が
・抵抗なく
・営業に行く
ようになります。
では、「その仕掛け」とは一体どんなものでしょうか?
それは、営業トークをしなくても、営業トークができる「パンフレット」を作ることです。
A4で1枚のパンフレットを作り、上から読むだけで「営業トーク」になるように設計します。読むだけなら誰でもできます。
そしてもうひとつ。「その場で紹介をもらえなくても大丈夫」と伝えます。
ほとんどの場合、営業に行ったその場で利用者を紹介してもらえる…なんてことはありません。ケアマネジャーは、後でもう一度パンフレットをじっくり読んだり、ネットで調べたりしてから、紹介候補の利用者がいるのか、誰なのかを考えます。
ですから、営業時のケアマネジャーの反応はあまり気にする必要はありません。
- パンフレットを読めば良い
- その場で紹介をもらわなくても良い
これでほとんどのリハビリ職は、積極的に営業に出てくれるようになります。